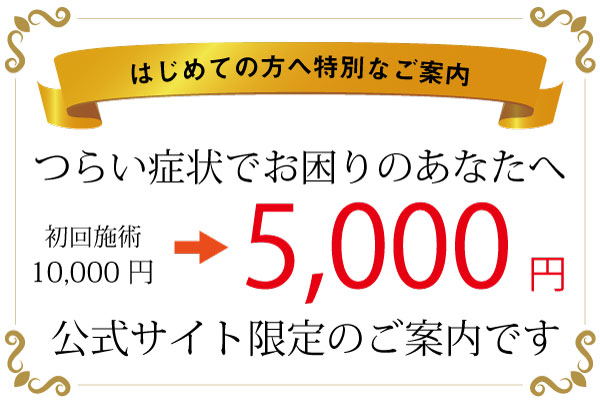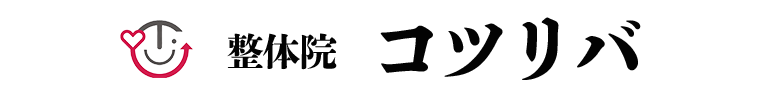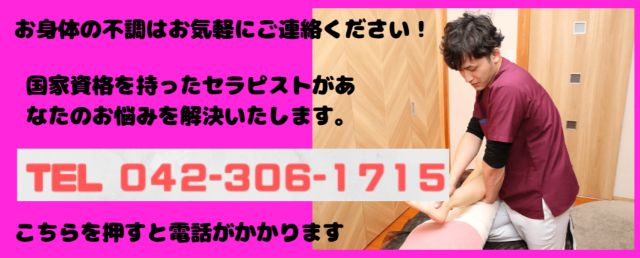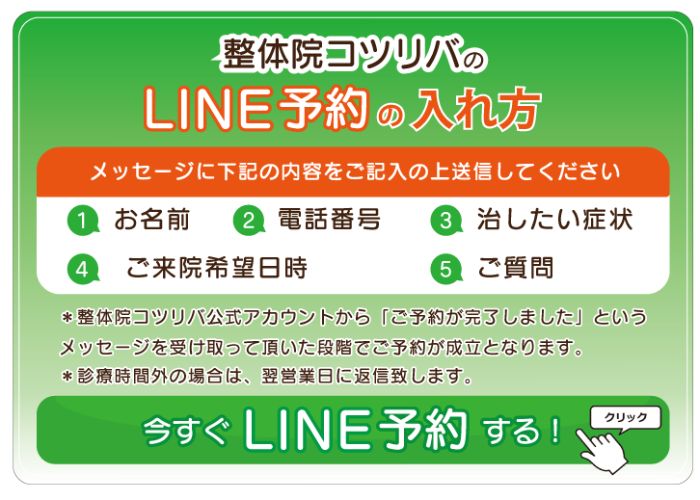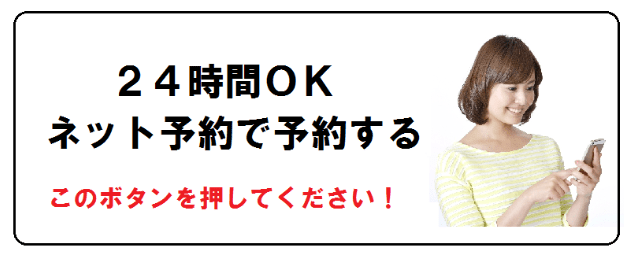多くの日本人を悩ませている肩こり。様々な原因がある中で、噛み合わせが原因となり肩こりになってしまっているケースも多数存在します。
本記事では、噛み合わせが原因によって起こる肩こりの原因や対策について解説します。
噛み合わせが悪いと肩こりが起こる仕組み

アゴの筋肉に疲労がたまると、近くにある首や肩の筋肉も疲労してしまいます。
力強く噛みしめると首や肩にも動くことでもわかる通り、筋肉は共同して働いているため噛み合わせが悪いと肩こりが起こる可能性があるのです。
ものを噛む力はとても強力であり、自身の体重に匹敵する力を持っていると言われます。更には、硬いものから柔らかいものまで対応しなければいけないため、筋肉には微細なコントロール力も求められます。
よって、歯の位置関係や形が悪いと食べ物を噛み砕いたりすり潰したりする際、うまく調整ができず力が入りすぎたり、コントロールできなくなることも。
結果として、筋肉の緊張や疲労が増し首や肩の筋肉までコリが広がってしまうことになってしまうのです。
噛み合わせが原因で起こる肩こり症状の特徴

一般的な肩こりと噛み合わせが原因で起こる肩こりの見分けはなかなか難しいのです。ここでは、噛み合わせが原因で起こる肩こりの見分け方を紹介します。
以下のような症状がある場合、噛み合わせが原因で起こる肩こりの可能性があります。
- 噛み合わせがしっくりこない
- 噛み合っていない部分が多い
- 噛んでいると疲れる
- 噛むと横にずれてアゴの位置が定まらない
- 噛みたい場所で噛めない
- 前歯が先に当たり奥歯が使えない
- アゴが曲がっている
- 大きく口を開けるとまっすぐ開いていない
- 顎関節症の既往歴がある
- 歯列矯正をしたことがある
上記に該当するものがあれば、噛み合わせが原因で起こる肩こりの可能性があります。その場合、本記事では紹介するセルフケアを実践してみることをおすすめします。
歯の矯正中でも肩こりがひどくなることはある?

歯の矯正中に肩こりがひどくなることがあります。矯正中は歯が移動しているため、筋肉のバランスが崩れやすいためです。
また、矯正器具によって痛みが発生してしまったにも肩こりの原因になる可能性があります。人間は痛みを感じると歯を食いしばって耐えようとするため、アゴや首・肩の筋肉が緊張し肩こりを発生させてしまうのです。
自宅でできる噛み合わせによって起こる肩こり対策法

ここからは噛み合わせによって起こる肩こり対策法をご紹介します。先に対策法の一覧を挙げると以下のようなものです。
- 左右の歯をバランス良く使う
- うつ伏せなどで顎に負担を与えない
- 歯のくいしばり、歯ぎしりを改善する
- マッサージで筋肉をほぐす
ひとつずつ紹介しています。
左右の歯をバランス良く使う
アゴの関節に負担をかけないためには左右の歯を均等に使うことが大切です。
食事をする際につい片側の歯で食べ物を噛んでしまいがちですが、片側ばかりを使う癖があると、関節に負担をかけてしまいます。
可能な限り左右バランスよく歯を使いましょう。
うつ伏せなどで顎に負担を与えない
うつ伏せや頬杖はアゴに負担がかかります。
特にうつ伏せは就寝時の姿勢の中でもアゴにかかる負担が高く、顎関節症になってしまう原因なってしまうことも。
頬杖もあごを下から上に突き上げる姿勢なので注意が必要です。アゴに負担がかかる姿勢は肩こりが悪化するので控えましょう。
歯のくいしばり、歯ぎしりを改善する
就寝時の歯ぎしりは肩こりを悪化させてしまうこともあります。
実は歯ぎしりは数十キログラム~100キログラムの力で噛みしめると言われています。しかし、就寝時は無意識なので自分で確かめることは難しいでしょう。
一つの目安として、歯ぎしりをする人は日中歯を食いしばる癖がある場合が多いため一度注意を向けてみても良いかもしれません。
また、歯ぎしり専用のマウスピースも販売されているため丈夫に活用しましょう。
マッサージで筋肉をほぐす
歯の噛み合わせが原因で起こる肩こりを改善したい方は口内マッサージもおすすめ。血流が良くなり、筋肉の緊張がほぐれやすくなります。
大きめのスプーンを用意し、頬の内側にスプーンの丸みを当て、頬を引き延ばすように上下に動かすことで簡単なマッサージが行なえます。左右ともに30回程行うのが良いでしょう。
まとめ
噛み合わせや癖によってアゴに負担がかかると、首や肩の筋肉に大きな負担がかかり、肩こりを助長してしまいます。
癖による負担を減らし、ケアを行うことで肩こりが軽減されることが期待できるので、積極的に取り入れてみましょう。